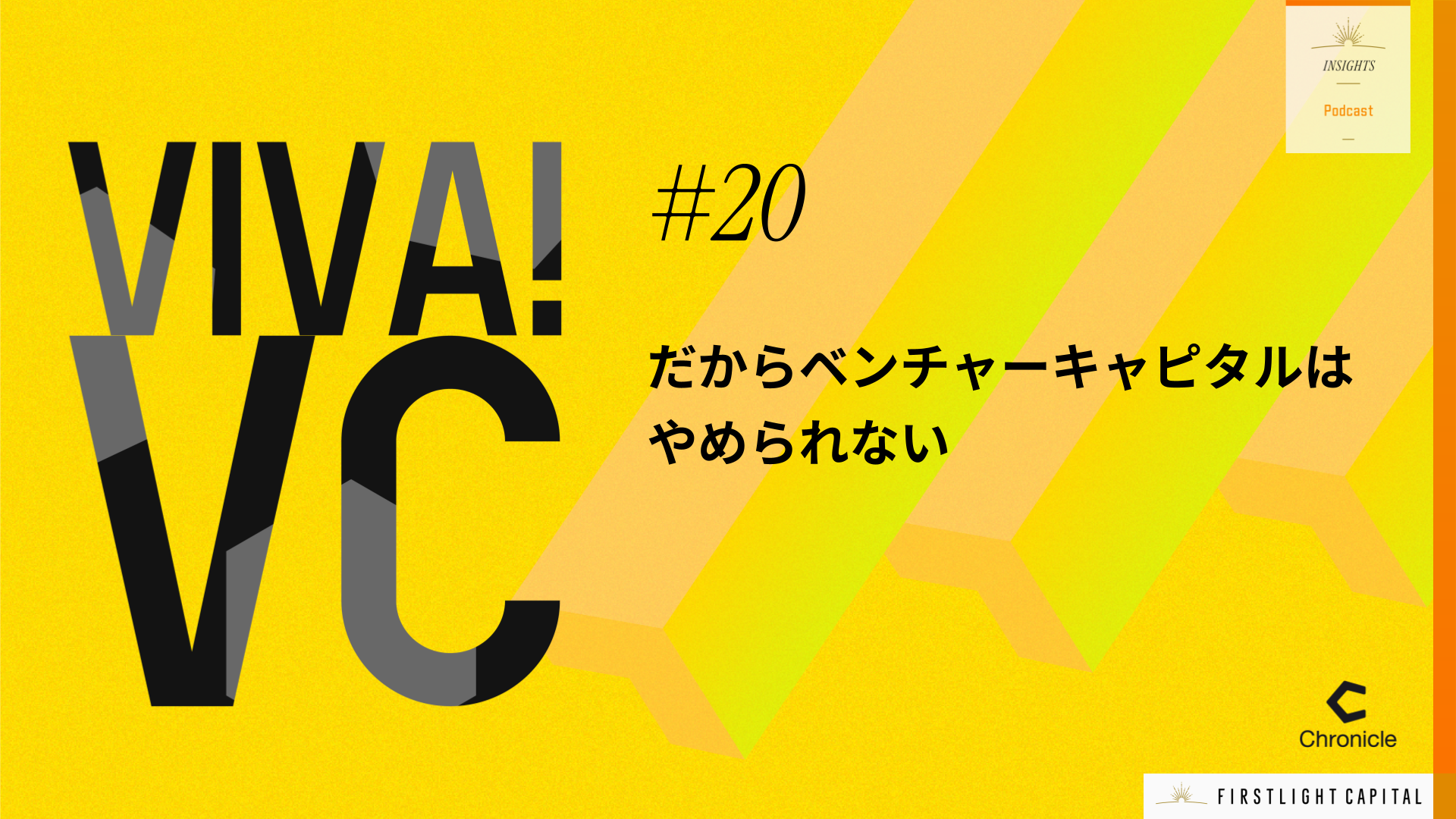
はじめに
少し前まで、スタートアップにおけるM&Aは「失敗の出口」としてネガティブに捉えられることが多く、VCが投資先にM&Aの可能性を示唆することは、慎重な扱いが必要とされていました。しかし、近年はその風潮が大きく変わりつつあります。2024年には、日本国内におけるスタートアップのM&A件数が174件に達し、10年前の84件から倍以上に増加しています。
本記事では、日本のスタートアップ業界においてM&Aが「前向きな選択肢」として受け入れられるようになった背景を紐解き、その実態や成功の条件について、具体的な事例とともに解説します。
※この記事はポッドキャスト「VIVA VC」第20回をもとに作成しました。番組では、スタートアップのM&Aについてさらに詳しく語っています。ぜひお聴きください。
M&A増加の背景にある3つの要因 [04:37-09:06]
まずは、現在のM&Aの全体像をデータで把握してみましょう。スピーダによると、2024年時点で日本のスタートアップM&Aは174件。また、事業やプロダクト単位の「事業譲渡」も76件に上り、こちらは10年前の19件から大幅な増加です。
このようなM&A件数の増加は、以下の3つの要因によって支えられています。
1. メガスタートアップによる買収の活発化
Sansanやマネーフォワードといった第一・第二世代のメガスタートアップが、自社の成長戦略の一環としてスタートアップの買収を積極的に行うようになってきました。米国でSalesforceやMicrosoftが実践している成長戦略型M&Aの流れが、日本でも広まりつつあります。
2. プライベートエクイティファンドの本格参入
Carlyleによるユーザベースやカオナビの買収、EQTによるHRBrainへの投資など、PEファンドによるスタートアップ買収が増加。これにより、M&Aはより多様な出口戦略の一つとして定着しつつあります。
3. スタートアップ自身によるロールアップ戦略
最近では、スタートアップが自身の成長戦略としてM&Aを活用する「M&Aロールアップ」が注目を集めています。GENDAがゲームセンター業界で複数企業を買収して成長したように、アーリーステージでも同様の動きが増加中です。ファーストライトの投資先であるクアンドやPeopleXも、地域企業や人材会社を買収し、成長を加速させています。
クアンド、宮崎県を拠点とする「南都技研」を完全子会社化、地方建設業の変革に挑む>>
PeopleX、ミーティングマネジメントツール「MeetingBase」事業を買収>>
M&Aに対するイメージの変化 [09:55-11:32]
かつて、VCがM&Aを持ち出すことは「VCとしてIPOを諦めたのか?」という否定的な反応を招くことが多く、話題にしづらいテーマでした。しかし今では、M&Aが「戦略的な成長手段」として広く認識されるようになってきています。
特に、シナジーのある相手との統合により、単独で進めるよりも大きな価値を生む可能性があるという認識が広がっています。「M&A=敗北」ではなく、「M&A=成長の加速装置」として捉えられるようになったことが、イメージの変化を後押ししています。
成功するM&Aの3つの条件 [12:13-17:03]
とはいえ、M&Aがすべて成功するわけではありません。むしろ、成功率は決して高くないのが現実です。失敗の原因の多くは、実は買収される側ではなく、買収する側にあります。私がユーザベースでM&Aを経験した際にも感じたのですが、買収する側は往々にして期待値を高く持ちすぎてしまいます。 「一緒になったらこんなことができるはず」という夢を描きすぎて、実際にM&Aした後に「なぜ変わってくれないんだ」「こんなはずじゃなかった」となるケースが非常に多いのです。私の経験から、成功するM&Aには以下の3つの条件が必要だと考えています。
1. 自走できる会社であること
買収後も自立して事業運営ができるかどうかが重要です。自力で利益を出せない会社を買収しても、その後も資金を注入し続けなければならず、買収側にとって大きな負担になります。M&A後も成長を続けられる体制が整っている会社こそ、M&A後も成長が期待できます。
2. 買収側が過度な変化を求めないこと
M&A後に「買ったからにはこうしてほしい」と過剰な期待や変更を求めるのではなく、「今のままでいい、必要なら我々のアセットを使ってください」という柔軟な姿勢が、長期的な成功に繋がります。
3. 手触り感のある領域でのM&A
経営者自身がしっかりと理解し、関与できる事業領域でのM&Aであることも成功の鍵です。事業があまりに異なると、マネジメントが難しくなり、統合がうまくいかないケースが多いのです。
VCから見たM&Aの実態 [20:00-22:30]
M&Aには、VC特有の視点も存在します。例えば、「優先株」の仕組みがあります。VCは一般的に優先株で投資を行っており、M&Aでの売却金は出資ラウンドの後期(例:D種、C種など)から順に分配されます。
例えば、10億円でM&Aが成立した場合、まずD種株主が取り、次にC種株主……というように順に分配され、最後に普通株を持つ創業者に渡る仕組みになっています。そのため、売却金額によっては、創業者の手元にお金が残らないケースも発生します。
また、M&AについてVCと起業家でディスカッションすることも重要です。私自身、投資先と事業計画を作る際には、必ずM&Aのオプションについても議論するようにしています。「事業がこういう状況になったら、M&Aも選択肢として考えましょう」というコミュニケーションを初期から行うことが大切だと考えています。
おわりに
日本においても、M&Aがスタートアップにとって自然な成長オプションとして受け入れられつつある現在、その存在はより前向きなものとして再定義され始めています。起業家にとっては2回目、3回目のチャレンジにつながり、VCにとっては早期のリターンにつながる。こうした流動性の高まりは、エコシステム全体の活性化につながります。
M&Aは「うまくいかなかったから売る」選択肢ではなく、「より早く、より大きく成長するための戦略的選択」です。VCとしても、M&Aを積極的に議論に取り入れることが、スタートアップの成長支援において重要になってきています。日本でもこうした認識が広がることで、より健全で活発なスタートアップエコシステムが形成されていくことを期待しています。
※この記事はポッドキャスト「VIVA VC」第20回をもとに作成しました。番組では、スタートアップのM&Aについてさらに詳しく語っています。ぜひお聴きください。
編集:ファーストライト・キャピタル SaaS Research Team
2025.5.19
ファーストライト・キャピタルでは、所属するベンチャーキャピタリスト、スペシャリストによる国内外のスタートアップトレンド、実体験にもとづく実践的なコンテンツを定期的に配信しています。コンテンツに関するご質問やベンチャーキャピタリストへのご相談、取材等のご依頼はCONTACTページからご連絡ください。
ファーストライト・キャピタルのSNSアカウントのフォローはこちらから!








