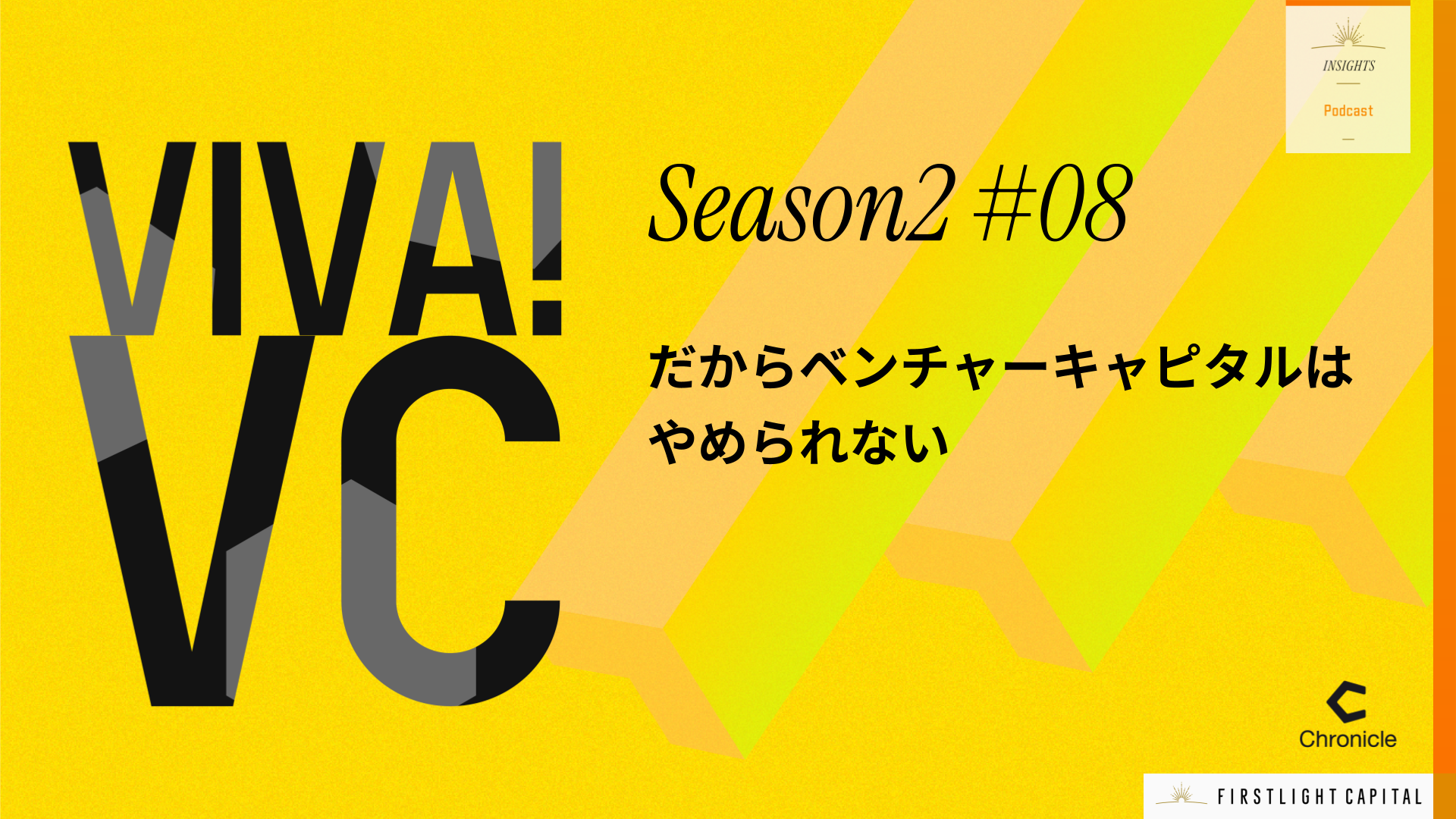
はじめに
AIが医療分野で急速に進化し、医師の業務を根本から変えつつある―そんな時代が、もう目の前に来ています。
今回は、アメリカで急成長を遂げる医療AIスタートアップの衝撃的な最新動向と、そこから見えてくる日本の医療が抱える構造的課題、そしてその解決策としてのAIの可能性について深く考察します。VCの視点から、この巨大な変革の波をどう捉え、どこにビジネスチャンスを見出すのかを解説していきます。
※この記事はポッドキャスト「VIVA VC」シーズン2第8回をもとに作成しました。番組では、医療AIの未来と日本の可能性について詳しく語っています。ぜひお聴きください。
評価額7600億円の衝撃。医師を「記録業務」から解放するAIユニコーン「Abridge」[03:47-10:19]
「Abridge(アブリッジ)」というスタートアップの名前をご存知でしょうか。医療業界において、今まさに「AIスタートアップの代表格」として注目を集める企業です。
2025年6月、Abridgeは著名VCであるアンドリーセン・ホロウィッツなどから430億円(3億ドル)という巨額の資金調達を実施し、その企業価値は約7600億円(53億ドル)に達しました。特に驚くべきは、わずか5ヶ月で企業価値が倍増したという、その凄まじい成長スピードです。
創業者のシブ・ラオ氏は、心臓専門医から起業家へと転身した人物です。彼が2018年の創業時に解決しようとしたのは、医師であれば誰もが直面する根深い課題でした。それは、「患者さんとの会話内容を手書きや手入力でカルテに記録する」という、膨大で時間のかかる作業です。
病院で診察を受けた際、医師がずっとパソコンに向かってカルテを打ち続け、なかなか目も合わせてくれない、という経験をしたことがある方も多いのではないでしょうか。診察室におけるこの光景を、Abridgeの「会話記録AI」は一変させます。
診察時にアプリを立ち上げるだけで、医師と患者の会話をAIがすべて記録。独自のLLM(大規模言語モデル)がその内容を自動で電子カルテ用に分類・文章化し、さらには処方箋まで作成します。医師はもはやタイピングに追われることなく、ただ「話すだけ」でよくなり、本来最も重要であるはずの患者との対話に集中できるのです。
この革新的なサービスがもたらした効果は、具体的な数字にも表れています。
- 記録業務が1日あたり「2時間削減」
- 医師の認知的な負荷が「78%減少」
- 燃え尽き症候群(バーンアウト)の発生率が最大「40%低下」
医師の負担を劇的に減らすことは、病院経営の観点からも医師の退職リスクを低減させ、組織全体のエンゲージメント向上に繋がります。現在、アメリカの150以上の医療グループが導入し、今年中には5000万人以上の診療データが処理される見込みです。
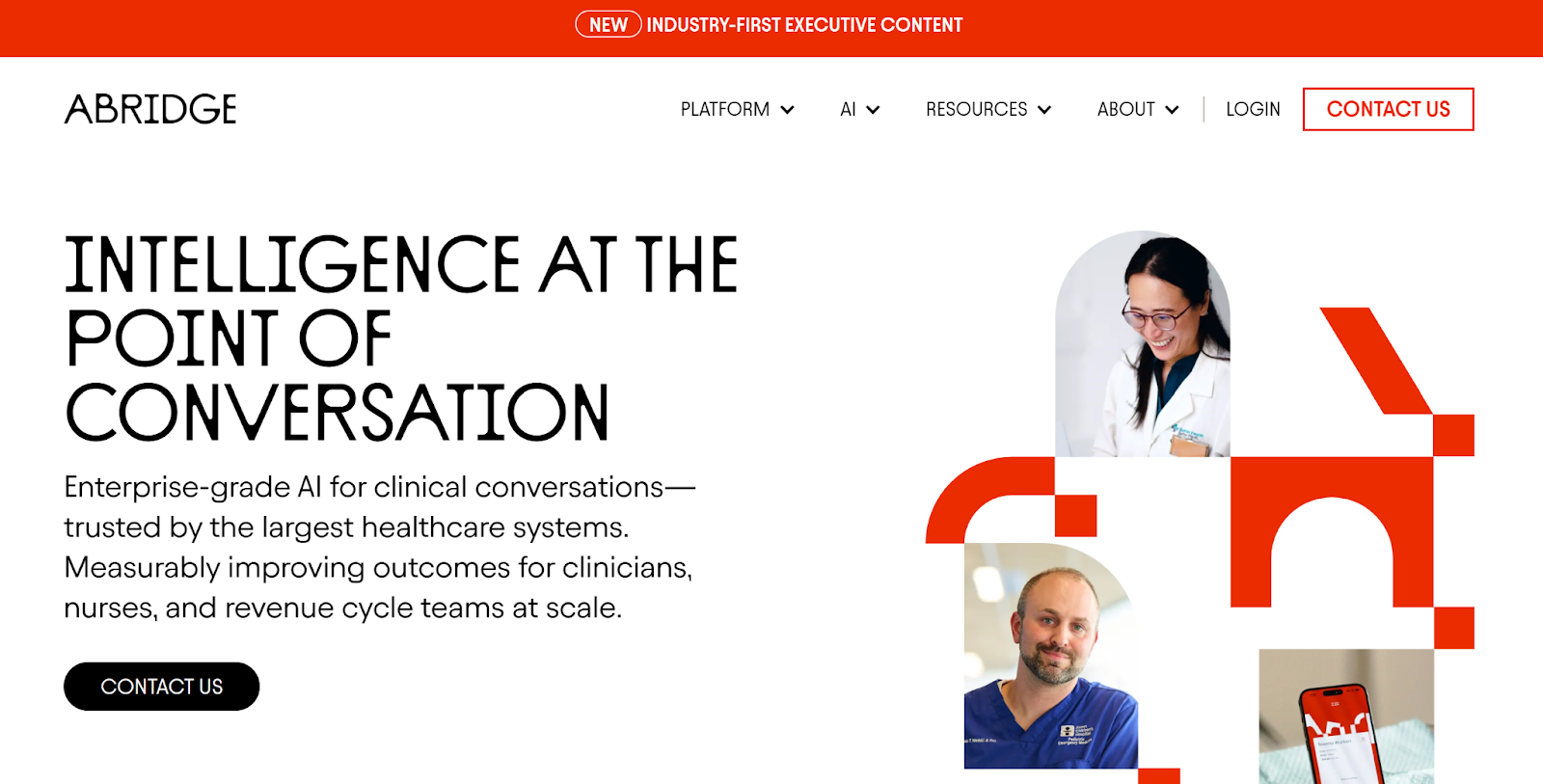
* Abridge: Generative AI for Clinical Conversations
診断精度は人間の4倍。マイクロソフトが示すAIの圧倒的な実力[10:24-13:58]
さらに衝撃的なニュースが、2025年6月にマイクロソフトから発表されました。同社が開発する診断支援AI「MAI-DxO」のテスト結果が、医療界に大きなインパクトを与えたのです。
複雑な症例における診断精度をテストしたところ、MAI-DxOは「85.5%」という高い正答率を記録しました。一方で、同じ条件下における人間の医師の正答率は約「20%」でした。もちろん、実際の診療現場では、医師は他の専門医にアドバイスを求めるなど様々な手段を組み合わせて診断精度を高めます。しかし、「個人のその場の知識・技術だけ」という制約下で比較した際、AIの能力が圧倒的であることは疑いようがありません。
MAI-DxOの真価は、単に診断するだけに留まりません。どの検査を、どのような順番で行うべきかまで提案するなど、「診断のプロセス全体をマネジメント」するのです。
アメリカでは医療費の約25%が不要な検査や事務手続きに費やされていると言われ、これはGDPの5%に相当する巨額のコストです。AIによる検査の最適化は、この医療費問題を解決する強力な切り札として、大きな期待が寄せられています。
AIは医師の仕事を奪うのか?「ヒューマン・イン・ザ・ループ」という理想的な協業 [14:00-15:56]
一方で、AIの導入には慎重に設計すべき課題も存在します。ある研究によれば、「AIと人間が協働すると、むしろAI単独よりも精度が下がることがある」というのです。AIの判断と自らの判断が異なった際に、「自分は間違っていないか」と医師が悩む時間が増え、かえって認知的な負荷が増大するケースがあるためです。
ここで重要になるのが、「ヒューマン・イン・ザ・ループ」という考え方です。これは、AIによる自動化のプロセスの中に、人間の判断や介入を意図的に組み込む設計思想を指します。AIの強みと人間の強みをどこで融合させるか、この設計こそが医療AI活用の鍵を握ります。
技術の進化とデータの蓄積により、この「人間とAIのいい塩梅」は必ず見つかるはずです。診断だけでなく、高齢者の日々の生活習慣の改善までAIがサポートすることで、「よりスマートで、より安全で、より健康な生活の質」が実現できるでしょう。
舞台は日本へ。超高齢社会の課題を解決する「医療AI」の可能性 [16:02-19:57]
アメリカの事例を見てきましたが、舞台を日本に移すと、また違った課題とチャンスが見えてきます。それは、世界でも類を見ない「少子高齢化」という現実です。日本の医療需要は、慢性疾患や多剤併用といった「長く・重く・繰り返す」性質のものが大半を占め、これが医療費を押し上げる大きな要因になっているといいます。
しかし、この日本特有の課題こそが、世界に先駆けたイノベーションを生む土壌となり得ます。現在、日本の医師のAI活用率は診断補助の領域で7〜11%程度に留まっており、導入の余地は非常に大きいと言えます。特に「高齢者医療に特化したAI」の開発は、日本の大きな強みとなる可能性があります。
ある医療関係者が「日本特有の課題をクリアしたイノベーションは、世界から注目される」と語っていたように、今後同様の人口減少社会を迎える韓国、ドイツ、中国などへの展開可能性は極めて高いのです。
また、増大し続ける医療費問題への切り札としてもAIは期待されています。2025年7月には、日本でも「がん診断にAI解析を活用し、医師不足に対処する」という動きが出てきました。人手不足という危機が、皮肉にも技術革新を後押ししているのです。「病院で1時間も2時間も待つお年寄りが多い」という現状も、遠隔診療とAIを組み合わせることで、離島医療の課題解決も含めて大きく変わる可能性があります。
おわりに
「医療は、人々の安心・安全に密接に関わっています。先生たちの人手不足で医療水準が落ちてしまうことが、社会にとって一番の課題です。」
だからこそ、AIの力で医療現場を効率化し、医療水準そのものを引き上げ、国民一人ひとりの生活の質を向上させることが今、求められています。
私たちVCは、この「医療×AI」の領域は、今後3〜5年が非常に大きなチャンスだと考えています。海外の先進事例を注視しつつ、日本ならではの課題解決から生まれる医療AIイノベーションを、力強く支援していきたい。そんな気概を持った起業家の登場を、心から期待しています。
私がAIに健康相談をすることが当たり前になる日は、そう遠くないかもしれません。その時、医師という職業の価値は決して失われるのではなく、より人間にしかできない領域―患者に寄り添い、共感し、勇気づける―といった、本質的な役割に集中できるようになるのではないでしょうか。
※この記事はポッドキャスト「VIVA VC」シーズン2第8回をもとに作成しました。番組では、医療AIの未来と日本の可能性について詳しく語っています。ぜひお聴きください。
執筆 : 岩澤 脩 | ファーストライト・キャピタル 代表取締役・マネージングパートナー
編集 : ファーストライト・キャピタル | リサーチ・チーム
2025.9.10
ファーストライト・キャピタルでは、所属するベンチャーキャピタリスト、スペシャリストによる国内外のスタートアップトレンド、実体験にもとづく実践的なコンテンツを定期的に配信しています。コンテンツに関するご質問やベンチャーキャピタリストへのご相談、取材等のご依頼はCONTACTページからご連絡ください。
ファーストライト・キャピタルのSNSアカウントのフォローはこちらから!








