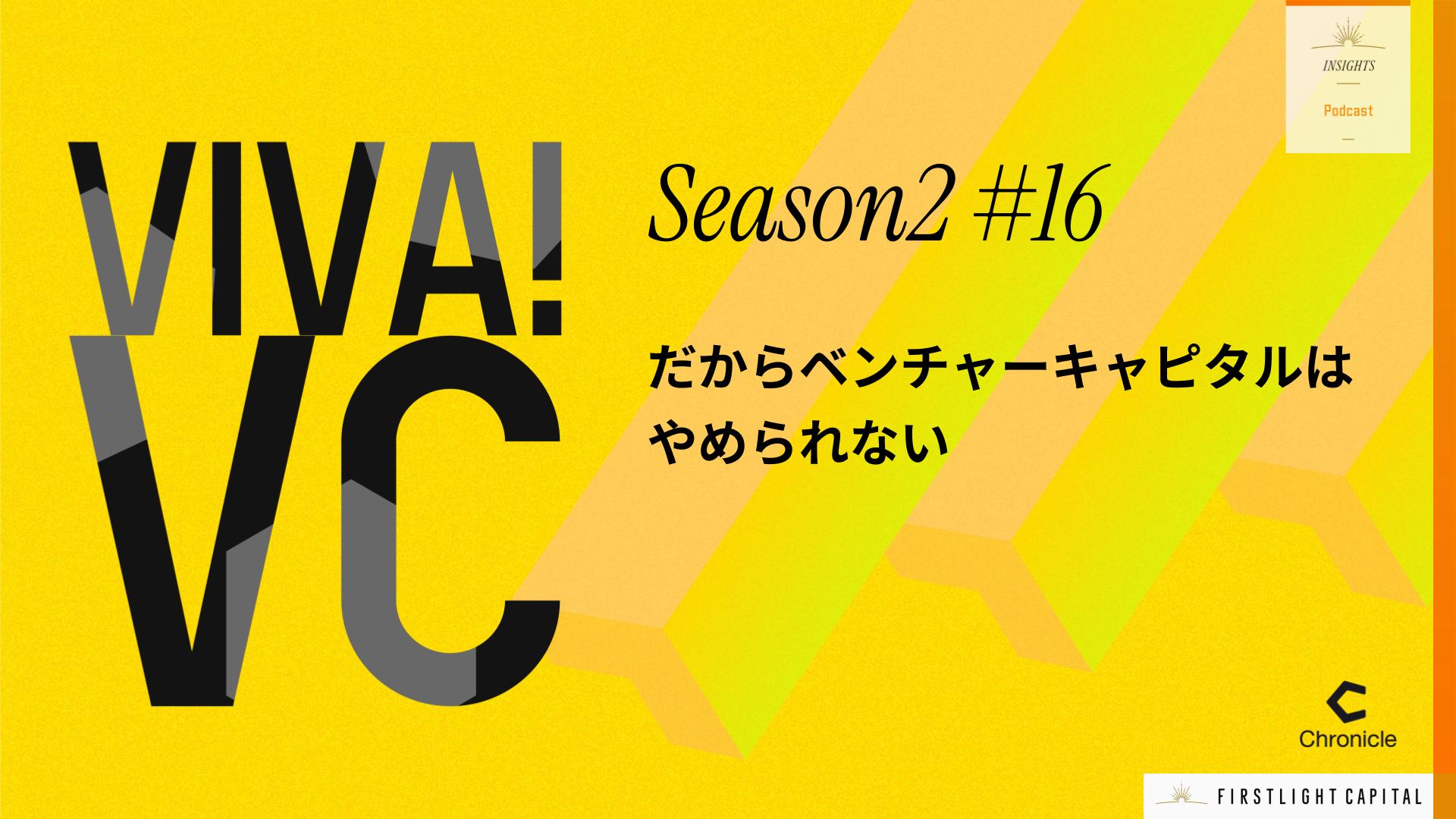
はじめに
スタートアップの世界では、「5ヶ月で評価額が倍増」「150億円の資金調達に成功」といった大型調達のニュースが華々しく報じられます。こうした見出しは、起業家にとって夢のように聞こえるかもしれません。しかし、一見すると輝かしい高額調達には、見落とされがちなリスクが潜んでいます。
今回は、スタートアップの資金計画の根幹である「資本政策」の基本から、昨今見られる「過剰な資金調達」がもたらす副作用まで、ベンチャーキャピタル(VC)の視点から深く解説します。魅力的な大型調達が、なぜスタートアップの未来を危うくする可能性があるのか、その真相に迫ります。
※この記事はポッドキャスト「VIVA VC」シーズン2第16回をもとに作成しました。番組では、資本政策の重要性についてさらに詳しく語っています。ぜひお聴きください。
「100億円を調達」と「100億円で調達」の違い[04:13-07:57]
まず、スタートアップの資金調達ニュースを正しく理解するために、非常に重要な二つの表現の違いを整理します。それは、「○○億円を調達」と「○○億円で調達」という、助詞の「を」と「で」の違いです。
「100億円を調達」と書かれている場合、これはシンプルに、新たに入ってくる資金、つまり「調達金額」が100億円であることを意味します。
一方、「100億円で調達」と書かれている場合、これは「企業価値(上場企業でいう時価総額に相当)」が100億円と評価された上での調達を意味します。
この二つを組み合わせた具体例で考えてみましょう。「100億円を1000億円で調達した」というニュースがあった場合、その内訳は以下のようになります。
- 調達前の企業価値(プレバリュー): 900億円
- 調達金額(今回集めたお金): 100億円
- 調達後の企業価値(ポストバリュー): 1000億円
- VCの株式保有比率: 10%
つまり、「1000億円で調達」とは、調達後の企業価値(ポストバリュー)が1000億円になる、という意味です。ニュースを読む際は、その数字が「調達金額」なのか「企業価値」なのかを意識するだけで、そのディールの規模感をより正確に理解することができます。
資本政策の「健全な姿」と、日本で起きる「異変」[08:00-12:56]
「資本政策」とは、スタートアップが成長していく過程で、「いくらの企業価値で」「いくらを調達し」「いつ調達するか」を計画的に設計することです。シード、シリーズA、B、C……とIPO(新規株式公開)に至るまで、事業成長に必要な資金をどのタイミングで集めていくかという、「上場までの資金調達ロードマップ」そのものを指します。
私たちが1000件以上のSaaSスタートアップの資金調達を分析したデータによれば、日本のスタートアップが健全に成長していく場合、各ラウンド間の期間(ランウェイ)と企業価値(ポストバリュー中央値)は、以下のような推移を辿るのが一般的です。
- シリーズAからBまで: 約1年半、ポストバリュー12.2億円
- シリーズBからCまで: 約2年、ポストバリュー29億円
- シリーズC: ポストバリュー50億円

「SaaS Annual Report 2024-2025」より
このように、1〜2年ごとに着実に企業価値を高めながら、連続的かつ持続的に資金を集めていくのが、健全な資本政策の姿です。
しかし最近、特にアーリーステージ(事業の初期段階)において、この健全な姿を脅かす「異変」が見られます。それは、本来の実力値を超えた高い評価額で、大型の資金調達を行うケースが増えていることです。
起業家にとって、VCから高い評価を受け、多額の資金を得ることは一見喜ばしいことに思えます。しかし、必要以上の資金を実力不相応な評価額で調達してしまうと、次回の調達時に評価額を上げることができず、企業価値が横ばいになる「ブリッジラウンド」や、前回を下回る「ダウンラウンド」に陥るリスクが急激に高まるのです。
過剰調達の背景と「ダウンラウンド」の深刻な影響[12:58-18:45]
では、なぜこのような過剰な調達が起きてしまうのでしょうか。背景には、日本特有の需給バランスの問題があります。資金調達できるスタートアップの数が減少傾向にある一方で、VCの数は増加しているため、起業家にとっては「売り手市場」となり、資金調達がしやすい環境が生まれているのです。
さらにVC側の構造的な事情も絡んできます。VCファンドの投資期間は通常5年程度と決まっており、その期間内に資金を投資し切る必要があります。そのため、起業家が本当に必要としている金額以上を、VC側の「予算消化」の都合で投資してしまい、結果として過剰調達になってしまうケースが散見されます。
では、過剰調達の結果として起こる「ブリッジラウンド」や「ダウンラウンド」は、なぜそれほど深刻なのでしょうか。
米国の調査データによれば、ブリッジラウンド(企業価値が横ばい)を経験した企業が、そこから次のラウンドに進める確率は、わずか8%しかありません。一度「成長が止まった」と見なされると、そこから抜け出すのは極めて困難なのです。
ダウンラウンド(企業価値の下落)に至っては、さらに深刻です。市場から「失敗の烙印」を押されたも同然となり、新規のVCから資金が集まらなくなるだけでなく、既存のVCの評価も下がってしまいます。
しかし、最も深刻な影響は「従業員の離脱」です。ダウンラウンドを経験した企業に対し、従業員、特に優秀な人材は「ここにいても未来がない」と判断し、次々と会社を去っていきます。これは、プロサッカーチームがJ2に降格した途端、主力選手が移籍していく現象と非常によく似ています。こうして悪循環に陥ると、事業の立て直しは一層困難になります。
健全な資本政策とは、「最良のパートナー」を見つけること[19:01-21:35]
では、スタートアップが目指すべき「健全な資本政策」とは何でしょうか。それは、一時的な高評価や大型調達を追い求めることではありません。事業が成長していく中で、本当に必要なタイミングで、本当に必要な資金を、信頼できるVCから調達していくことです。
「健全な資本政策を描きましょう」「低いところから積み上げましょう」と言うと、「VCが多くのシェアを取りたいだけのポジショントークだろう」と聞こえるかもしれません。
しかし、VCが本当に見ているのは、目先のシェアではなく、「そのスタートアップが、安定的かつ連続的に資金を調達し、IPOまで成長し続けられるか」という点です。そのためには、VCと起業家が膝を突き合わせて真摯に話し合い、強固な関係性を築く必要があります。
資金調達は、どのVCが最も高い評価額をつけるかを競う「ビューティーコンテスト」ではありません。IPOまでの長い道のりを見据え、どのような資金計画で事業をブーストさせていくか、その戦略を共有できるパートナーを見つけることこそが重要なのです。
おわりに
今回の話を一言でまとめるなら、「最高のバリュエーション(評価額)を提示するVCは、最良のパートナーとは限らない」ということです。
高い企業価値や大きな調達金額は、それ自体が目的ではありません。アメリカの失敗事例から私たちが学ぶべき教訓は、「資金調達のための事業作り」ではなく、「事業成長のための資金調達」という本質を決して忘れてはならない、ということに尽きます。実際、こうした反省から、米国のアーリーステージの起業家の中には、あえてVCマネーに頼らず事業を立ち上げるマインドセットに回帰する動きも見られます。
資本政策は、一度実行すると取り返しがつきません。目先の大きな数字に惑わされることなく、長期的な視点で自社にとって本当に必要な資金調達を見極めること、それこそがスタートアップの成功に不可欠なのです。
※この記事はポッドキャスト「VIVA VC」シーズン2第16回をもとに作成しました。番組では、資本政策の重要性についてさらに詳しく語っています。ぜひお聴きください。
執筆 : 岩澤 脩 | ファーストライト・キャピタル 代表取締役・マネージングパートナー
編集 : ファーストライト・キャピタル | リサーチ・チーム
2025.11.3
ファーストライト・キャピタルでは、所属するベンチャーキャピタリスト、スペシャリストによる国内外のスタートアップトレンド、実体験にもとづく実践的なコンテンツを定期的に配信しています。コンテンツに関するご質問やベンチャーキャピタリストへのご相談、取材等のご依頼はCONTACTページからご連絡ください。
ファーストライト・キャピタルのSNSアカウントのフォローはこちらから!








