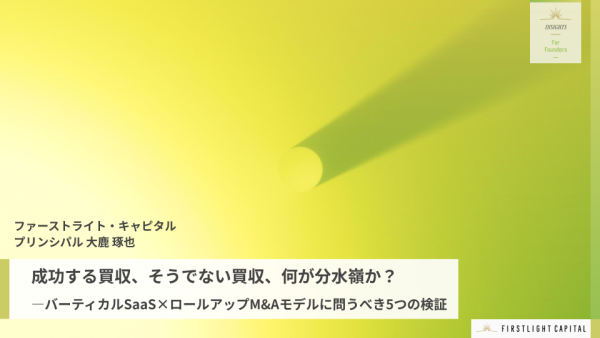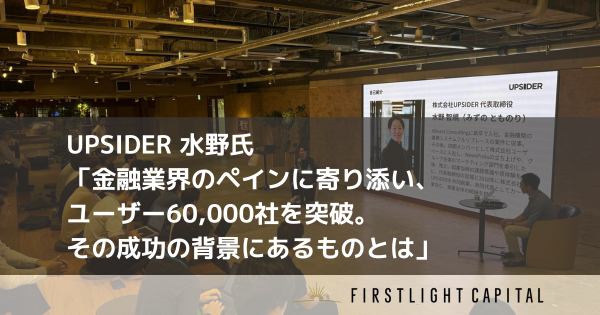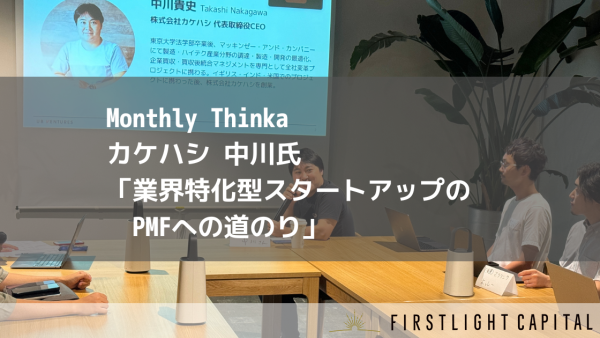保育・教育・介護等のライフサポート業界の人材不足、労働環境のアナログ性は社会課題として注目されている。課題解決に対する社会的なニーズも大きい領域である一方で、法規制の影響が強く、最先端技術の導入ハードルが高い業界でもある。これらの業界においては、突き抜けたプロダクトによる明確な課題解決が重要となる。
日本の産業を進化させるというミッションのもと、起業家向けソーシャルクラブ「Thinka」をアップデートした「Thinka+」では、2025年4月に第2回のイベントプログラムを開催。
ユニファ株式会社代表取締役CEO・土岐泰之氏をお招きし、「ライフサポート業界」をテーマに、ユニファのプロダクト開発ストーリーやPMFまでのポイントについて学びを深めた。
本記事では、クローズドなディスカッションの中から、外部公開の許諾が得られた内容に限定し、コンテンツ化していく。
ライフサポート領域でIT化が進みにくい理由は「業界構造」にある
――まずは、土岐さんに事業説明をいただきたいと思います。
土岐:私が代表を務めるユニファという会社は、「家族の幸せを生み出す あたらしい社会インフラを 世界中で創り出す」というパーパスを掲げて事業を展開してきました。非常に大きなテーマですが、このパーパスの吸引力によって、これまでの経営が成り立ってきたと感じています。
当社は約12年前の2013年に創業しました。当時、私は愛知県豊田市に住んでおりました。妻の仕事や家庭の事情があり、縁もゆかりもない豊田市で、一人で起業したのです。
現在までに100億円近い資金調達を行い、200名以上の規模で事業を展開していますが、12年の間には倒産の危機や組織崩壊、プロダクトのシステムバグなど、あらゆる問題に直面してきました。
私自身は、商社やコンサルティング会社などで勤務していた頃から「起業したい」という思いはずっと持っていたものの、テーマが見つからない状態でした。そんな中でこどもが生まれ、共働きで子育てをする大変さを実感するとともに、「家族」こそが自分のテーマだと気づき、この領域で起業しました。
現在展開しているプロダクトについても紹介させてください。
当社のプロダクト『ルクミー』は、「こどもをもっとルック・アット・ミー(見て)してあげよう」という意味を込めて名付けたものです。最初は、保育者やカメラマンが撮影した写真をインターネットで閲覧できるサービスとしてスタートしました。
その後、保育者の方々が写真以外の業務でも様々な苦労を抱えていることがわかり、現在では全部で15個ほどのプロダクト機能を提供するようになりました。朝の送迎バスの位置情報、園での活動記録、登降園管理、体温チェック、午睡(お昼寝)中のチェック、各種書類作成など、保育業務全般をカバーしています。
最近では、これらのプロダクトに「AI」が急速に導入されつつあります。保育者が連絡帳やお便り帳を作成する際、例えば「遠足は〇月△日、場所は××」といった情報を入れるだけで、AIがお便りのドラフトを作成してくれます。他業界でも進みつつあるAIエージェントの世界が、保育の分野でも動き始めているのです。
このようなプロダクト開発の背景には、日本のこども数の減少問題があります。私は、日本の社会課題の中で最も優先順位が高く、最も深刻な問題は少子化だと考えています。日本ではこどもの数が増えるほど生活満足度が下がる傾向があり、こどもたち自身も諸外国と比較して自己肯定感が低い状況です。
この問題を解決しない限り、日本社会そのものが存続の危機に直面すると考えています。高齢者の医療費負担などの議論以前に、日本社会の存続自体が危ぶまれる状況なのです。
こうした問題にどのようにアプローチすべきか。まず、日中のこどものケアを担っている保育者の給与が低いという現実があります。2023年にこども家庭庁が設立されたものの、保育者の離職率は依然として高く、保育施設のあり方がしっかりと整備されなければ、子育て世帯も幸せになれません。
興味深いことに、小学生に将来なりたい職業を尋ねると、保育者は常に上位にランクインしますが、中学・高校・大学と年齢が上がるにつれて、順位は下がっていきます。
また、保育者が職場を去る理由を尋ねると、給与の低さは必ずしも1番の理由ではなく、「職場の人間関係」や「やりがい」も大きな要因として挙げられています。
こどもが大好きで保育者になったにもかかわらず、サービス残業の多さや手書き書類の煩雑さ、職場の人間関係の問題に悩まされているのです。これらの課題を考えると、給与が上がらないという経済的な問題と、精神的な負担の両方を解決していく必要があります。
――私もこどもを保育園に通わせていて、保育者の方々を心からリスペクトしています。しかし保育施設で行われている業務は、本当に臨機応変な対応が求められ、プロダクトで業務を置き換えることは非常に難しいのではないかと考えられます。
保育だけでなく、介護や医療などの分野でも同様で、そのような特性が原因でITの浸透が進みづらかった背景もあるのではないでしょうか。土岐さんが最初に保育業界に参入された際、保育業界の根本的な課題はどこにあったとお考えですか?
土岐:おっしゃる通り、保育施設の業務は標準化が難しい側面がありますが、それだけではありません。通常、飲食店やホテルなどのBtoCビジネスでは、経営のドライバーとなるのは顧客ですが、それは保育施設で言えば保護者にあたります。
しかし保育施設の場合、どのようなサービスを提供しても保育料の単価はそれほど変わりません。例えば100人規模の保育施設の売上は約1億円ですが、そのうち9割が国からの補助金で賄われているのです。補助金を受けるためには行政が行う「監査」をクリアしなければならず、逆に言えば監査さえクリアできれば経営は成り立つため、それ以上の効率化へのインセンティブが働きにくい構造がありました。
事業拡大のカギは、泥臭い「営業」とバーニングニーズを捉えたプロダクト開発
――保育だけでなく医療や介護など、公的補助金が多く使われている分野は、消費者にとってはありがたいことですが、事業者側がサービスをいくら向上させても、それに見合った報酬が得られないと。こうした状況の中で、どのようにしてユーザーに振り向いてもらったのでしょうか?
土岐:12年前に起業した当初から、保育者の忙しさやサービス残業の多さといった問題に着目していました。私はまず、明確な課題に対する明確な解決策、いわゆる「ワンペイン・ワンソリューション」を提供することが重要だと考えました。そして着目したのが写真管理です。
当時、保育者はデジタルカメラで写真を撮影し、SDカードのデータをパソコンにアップロードするという作業に膨大な時間を費やしていました。その後、写真を印刷して壁に貼ったり、印刷した写真を販売したりといった業務も発生していました。
そこには明らかな非効率があったため、データでアップロードできるシステムを提供することで、現場の方々に理解していただくことができました。
もちろん、最初のお客様を得ることは困難でした。無名の若い起業家が訪問しても最初は信頼を得られませんでしたから。地道な営業活動と、強いソリューションを提供すること、この2つが大きなポイントだったと思います。
――その2点についてもう少し掘り下げてお聞きしたいです。まず営業の観点から。最初の保育施設開拓はどのようにされたのですか?
土岐:縁もゆかりもない土地でしたので、自分のこどもが通う保育園の園長先生にも面会し、友人にも紹介をお願いしました。最初のお客様が見えてきたら、今度はその園長先生からの紹介を中心に広げていく。これを「園長テレフォンショッキング」と呼んで、とにかく営業活動を続けた結果、40〜50施設ほどの顧客を獲得することができました。
次に、より高度なテクノロジーを導入しました。例えば、数千枚ある写真の中から自分のこどもの写真を効率的に見つけられるような顔認識技術です。
技術的な強みを持ったことで、東京の大手企業からも関心を持っていただけるようになりました。上場企業からもコンタクトがあり、彼らの要望に徹底的に応えながら、一つずつステップを踏んでいった結果、大きく展開することができました。
――プロダクトの進化についてお聞きします。土岐さん自身がユーザーとしての原体験をお持ちでありつつも、市場に投入しながら学んでいかれた部分もあったと思います。最初はどの程度の手応えを感じられたのか、そこからどのようにアップデートを重ねていったのか、PMFの初期段階に向かうプロダクト開発についてお聞かせください。
土岐:いろんな失敗を重ねながら進化してきましたね。2つ目の主力プロダクト『午睡チェック』は、こどもたちのお昼寝中に使用するセンサー型のデバイスで、おへその上あたりに装着する形になっています。しかし、ここに至るまでにも様々な苦労がありました。
開発の動機は、午睡中の乳幼児突然死症候群(SIDS)などの死亡事故防止でした。保育現場を調査した際に衝撃を受けたのは、保育者が5分おきにこどもの体勢チェックを行い、手書きで記録していたことです。うつぶせ寝で窒息リスクがある場合や、咳が出た時、体勢を変えた時など、全員分を記録するのです。これを見て、「保育者が辞めるのも無理はない」と強く感じました。
保育施設には他にも様々な業務があるものの、命に関わる問題であることや監査対応という明確な課題があったため、午睡チェックに注力することにしました。しかし、このセンサー型のソリューションに辿り着くまでに1年以上を要したのです。
当初は様々なアプローチを検討しました。例えばベッドに敷くマット型センサーも開発しようとしましたが、ベッドを使っていない保育施設が多いという現実に直面し断念。カメラ型のソリューションも検討しましたが、こどもが毛布をかぶると検知できないという問題もありました。
着用型センサーが最適という結論に至ったものの、最初はデバイスが大きすぎて0歳児が泣いてしまうため苦戦しました。様々な改良を重ね、現在の形に落ち着いたわけです。
最終的にはこのプロダクト単体で一定の規模のビジネスに成長し、IoTを活用したサブスクリプションモデルとして確立しました。その後、国からの補助金も出るようになりました。
――命にかかわる課題に対し、これまでなかったソリューションを作り出されたことは、素晴らしいお取り組みだと思います。その過程では様々な苦労があったと思いますが、土岐さんがソリューションに辿り着くうえで、特に重要だったポイントは何でしょうか?
土岐:最も重要だったのは熱心なユーザーの存在、そして彼らの声を信じ切ったことだと思います。例えば、同時期に検討していた体温計測のソリューションについては、20施設ほどを訪問し、「月1,000円程度なら支払ってもいい」という回答を4割程度の園からいただきました。
しかし、乳幼児突然死症候群の問題と手書きの記録の煩雑さについては、はるかに切実な声があったのです。死亡事故をきっかけに保育者が退職してしまうケースもあるし、暗い部屋での見守り業務の負担も大きい。形状がどうあれ、負担を減らし、こどもの安全を守れる製品を「早く作ってほしい」と、現場の熱量が段違いでした。そうした声を信じ切ったことが成功の鍵だったと思います。
――バーニングニーズが明確にあったということですね。逆に、当時も保育施設向けにITプロダクトを提供している会社はあったと思いますが、なぜこの問題は解決されていなかったのでしょう?
土岐:『午睡チェック』を開発した頃はちょうどIoTの概念が注目され始めた時期でした。モノとテクノロジーを組み合わせたサービスがようやく実現可能になってきた頃です。私たちは基本的に、実際の問題解決に役立つならば技術トレンドを取り入れることは有効だと考え、IoT技術を導入することを決めました。
IoTのような物理的なデバイスが絡む場合は初期投資が大きくなりますが、シリーズBとCを合わせる形で計45億円程度の資金を調達し、技術開発と初期投資に充てることができました。この投資判断も重要なポイントだったと思います。
2つ目、3つ目のプロダクト検討では、領域の連続性よりも「ニーズのありか」を見極めよ
――写真サービスが1つ目のプロダクトで、午睡チェックが2つ目とのことですが、同じ保育分野でありながらもソリューションとしては大きくジャンプしている印象を受けます。通常はプロダクトを連続的に発展させていくことが多いと思いますが、異なる領域に挑戦されたのは何が理由だったのでしょうか?
土岐:もちろん当初は、プロダクトを自然につなげていこうという考えもありましたが、実際には失敗も多くありました。写真サービスが一定の広がりを見せた後、次のステップとして取り組んだのは連絡帳アプリでした。例えば「写真があるのだから、それを活用して園と保護者がやり取りする連絡帳アプリを作ればいい」と考えたのです。しかし、このデジタル連絡帳が全く売れなかった。
当時はまだガラケーを使用している保護者も多く、タイミングが早すぎたのです。保護者とのやり取りよりも、園内だけで完結する日誌や登降園管理などの方が、ソリューションとしてのニーズがありました。このように試行錯誤を繰り返しながら、先ほど述べたような切実なニーズがある午睡チェックに行き着いたというのが実際のところです。
――今の『ルクミー』の全体像を作り上げるまでに、プロダクトを連携させていく構想はどの段階から計画されていたのでしょうか?
土岐:これについても失敗の連続でしたが、『午睡チェック』を導入することで、睡眠時間のデータが取得でき、それを連絡帳に反映させることもできるようになります。そこに写真も関連させられるなど、徐々につながりが見えてきました。
そうした中で、当時他社が運営していた保育施設向け連絡帳アプリ『キッズリー』を買収しました。スマートフォンの普及も進み、「今こそ連絡帳アプリの時期だ」と考えたのですが、導入後にはいくつかの課題が見えてきました。既存の私たちのプロダクトと買収したアプリとのデータ連携やアカウント連携が難しかったことです。最終的には内製で改めて開発を進めることになりましたが、そのプロセスもまた容易ではありませんでした。ただ、当時の試行錯誤の経験が、今のプロダクト連携や開発に活かされていると感じています。
この過程で重要だったのは、プロダクト開発をリードする強力な推進力を持ったメンバーの存在です。組織内のコミュニケーション形成に時間をかけすぎるのではなく、とにかくプロダクトを立ち上げることに集中できる環境を意識的に創っていきました。
このフェーズでは推進力のあるメンバーに任せて突破する必要がありました。結果として、組織の能力も高めながら、プロダクト連携を実現することができました。
――ありがとうございます。プロダクト連携のところは非常に厳しい経営判断が求められる局面だったと思います。当時を振り返ると、何が足りなかったと感じますか?
土岐:一番の困難は、元の『キッズリー』アプリを開発したエンジニアがPMIの時に一人も自社に来なかったことです。
また、結果的に写真の価値が非常に高いことが分かったのですが、プロダクトデータの価値を早期に見極められればよかったと思います。写真1枚を撮れば、連絡帳にもお便り帳にも活用できる。この気づきによって、プロダクト間のコミュニケーションが共通言語化されていきました。
「連絡帳を10行書くよりも、文章は3行でいいから写真を3枚つけた方が保護者に喜ばれるよね」という考え方は、現場の保育者にも、もちろん保護者にも喜ばれ、マネタイズにも有効でした。このような「勝利の方程式」が少しずつ見えてきたことは大きかったと思います。
――写真がすべてのプロダクトの基盤となる価値になっているというお話は非常に興味深いですね。これはコンパウンドを実践し、データを連携させなければ気づかなかった洞察だったのでしょうか?
土岐:そう思います。保育者や園長先生は比較的シンプルな業務フローを持ちながらも、多種多様な業務を行っています。難しかったのは、どの順番、どの時間軸でデジタル化されていくかを見極めることです。私たちは当初、連絡帳が次に来ると思いましたが、実際には登降園管理が先でした。
順番と時間軸の予測は、国の補助金の出方や保護者のスマートフォン普及率など、様々な外部要因が絡み合っているので難しいのです。
経営者が「熱意を持って語れる」プロダクトをつくることが何より大事
――プロダクトの開発においては、プロダクトマネージャー(PM)の役割が非常に重要だと思います。PMの役割や体制はどのようにされていましたか?
土岐:私自身がPMを務めたのは、写真サービスと午睡チェックの開発時のみです。その後はPMをきちんと配置して進めてきました。ただ、創業者のキャリアバックグラウンドによって状況は異なると思いますが、経営陣、特に創業チームがプロダクト開発から逃げない方が良いと思います。
保育、介護、医療などのバーティカルDXでは、ある程度の規模を目指すならコンパウンド型は必然です。そうなると資金調達や組織構築も重要ですが、プロダクト自体への取り組みも欠かせません。
正直なところ、私は商社やコンサルティング出身でプロダクト開発は専門外でした。営業が得意であっても、プロダクト開発は苦手。それでも必死にPowerPointでワイヤーフレームを作り、時にはエンジニアに指摘されながら進めてきました。
こうして作ったプロダクトに対しては営業力が増しますし、その後の資金調達にも効果的です。苦手だと感じてもメンバーに任せきりにせず、問題解決への熱量をもって自らやり切ることが非常に重要だと思います。
――プロダクト開発を他のメンバーに託せるフェーズに移ったのはどのようなタイミングでしたか?また託すことでどんな変化があったのでしょうか。
土岐:『キッズリー』の買収後に連携の課題が発生した際、プロダクトのスケール的に私一人では対応しきれないと正直に感じました。その頃には事業規模も拡大し、採用活動も積極的に行えるようになっていたので、任せることにしました。
ただ、少し後悔している点もあります。任せすぎた結果、気がつくと自分自身がプロダクトに対して熱意を感じられなくなっていた時期が2年ほど前にあったのです。様々な機能を開発したものの、私たちのパーパスの実現につながっているのか、競合他社との本当の差別化になっているのか。『午睡チェック』開発時のような熱量が少し弱まっていた。
これはいかんと思い、現在では保育AIの開発などに熱意を持って語れるところに関わっていくよう意識しています。
具体的に取り組んでいるのは、園児別の成長記録など、こどもと家族のコミュニケーションを促進するサービスです。保育者が記録したテキスト情報や写真、その他のデータをAIで分析して可視化します。
例えば3ヶ月間で撮影した写真や保育記録からの要約、写真からのキーワード抽出などが自動的にまとめられることで、「最近ずっと積み木をしている」とか、「A君とよく一緒に遊んでいる」といった情報が全て把握できます。
こどもの生涯データとして残し、6歳で卒園した後も、10歳になっても20歳になっても見続けられる、「自分が愛された証」として残せるものにしたいと考えています。このような取り組みは創業期の熱量を思い出させてくれるものです。
――プロダクトは順調に育っていったものの、土岐さんご自身としては再び情熱を持てるプロダクトを作りたいと心から思われたということですね。
土岐:自分自身が熱意を持てないプロダクトでは、差別化が難しくなります。突き詰めて考えると、小手先の営業やマーケティングではなく、心の底から顧客課題の解決策を生み出すこと、つまり事業ビジョンとプロダクトの結びつきが重要だと思い至りました。
私たちは会社として改めてアクセルを踏むためにリスタートした2年ほど前から、ビジョンを言語化し、事業計画に落とし込めるようになりました。そして新しいサービスがまもなくリリースされる予定です。この過程で、組織全体にもビジョンが浸透してきました。
――赤裸々にお話いただきありがとうございます。では最後に、起業家の皆さんに向けてエールをいただければと思います。
土岐:私が最も大切だと思うのは、起業家の“ソース・オブ・エナジー”(エネルギーの源泉)です。今日お話ししたように、様々な困難や失敗はつきものです。私自身も苦しい時期がありましたが、最終的に自分のソース・オブ・エナジーをどう維持し続けるかが重要だと思います。それがなければ、誰も説得できません。株主も顧客も動かせません。
私の場合は、お客様からの「このままでは業界が持たない、ルクミー頑張って」という声が大きな力になりました。「家族の幸せのために」という思いや、応援してくれる人々の期待に応えるという気持ちで続けてきました。
エネルギーレベルが下がる時もあります。でも、ソース・オブ・エナジーがあり、それを組織に浸透させ、最終的に共に信じてくれる仲間が増えていけば、道なき道も切り開いていけるはずです。その核心部分さえ折れなければ乗り越えられます。
特に、ライフケアや社会福祉産業は時間がかかります。短期的には無理だと思われることでも、信じて取り組む姿勢を忘れないでください。
「これをやらないと死ねない」という強い思いこそ、とことん大事にしましょう。皆さんがいらっしゃるライフケア産業には、必ず大きな課題があるはずです。そこを大切にして取り組んでいただきたいと思います。
記事執筆:落合真彩
編集:ファーストライト・キャピタル SaaS Research Team
2025.5.16
ファーストライト・キャピタルでは、所属するベンチャーキャピタリスト、スペシャリストによる国内外のスタートアップトレンド、実体験にもとづく実践的なコンテンツを定期的に配信しています。コンテンツに関するご質問やベンチャーキャピタリストへのご相談、取材等のご依頼はCONTACTページからご連絡ください。
ファーストライト・キャピタルのSNSアカウントのフォローはこちらから!